

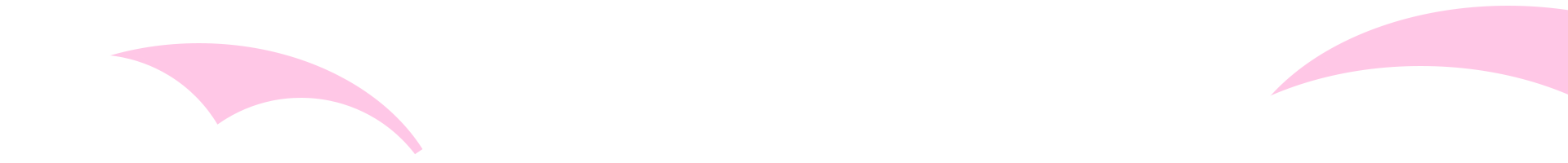
1年ほど前よりお伝えしているこちらの現場もまもなく竣工となります。
今日は久慈川が見守る中、社内のみんなで最終検査です!
現場経験が豊富な先輩たちが念入りにチェックしています。
縁石、コンクリート舗装、階段などなど...。
社内検査といえどもやはり検査というものは緊張します。
大きな是正箇所や指摘がないといいな...。
今日は涼しい室内でコンクリートの圧縮強度試験の見学です。
コンクリートの供試体に対して試験機で徐々に力を加えていき圧縮強度を測定します。
供試体が破壊される!と思い離れて見てましたが、ヒビが入ったところでストップ!
隣にある目玉おやじみたいな検力器が示す最大荷重等から圧縮強度を算出します。
3個の供試体の圧縮強度を測定し平均した値が1回の圧縮強度となります。
十分な強度で試験結果は合格でした!
昔々、日本には天照大御神という太陽を司る神様がいました。
怒って岩の中に引きこもり世の中を真っ暗にしちゃったのは有名ですね。
現代では、私たち作業員が頼るのは神様ではなく「総合気象GISプラットフォームAmatellus(アマテラス)」。
アマテラスは現場の気象変化を迅速かつ詳細に予測し地図上でわかりやすく可視化します。
今時期は梅雨や台風による降雨で河川が増水しやすい出水期です。
アマテラスで気象情報や予想される水位などをチェックして作業の実施や中断を判断しています。
7月に入りいよいよ夏本番!
パラソルが並んでますがここはビーチではありません。
炎天下で働く作業員のために、工事現場にパラソルが設置されています。
ありがたいのがミストファン。霧状のミストが周囲の温度を下げてくれるのです。
パラソルとミストファンでクールダウンして熱中症を防ぎます。
覆土ブロックの布設が完了し、いよいよ土を被せる時がきました。
ブロック表面の凸凹がまるで龍のうろこのようで綺麗です。
この凸凹のおかげで覆土が滑らず安定します。
こんなに綺麗に布設したのにもう埋めてしまうんですね。
別れを惜しむ間もなくとんどん土を被せています。
覆土ブロックの布設が着々と進んでおります。
今日は法面下部に間詰コンクリートを打設しました。
打設したコンクリートをきれいに均し、表面養生剤を散布していきます。
表面養生剤は、コンクリート表面からの水分蒸発を抑制し、乾燥収縮によるひび割れを防ぎます。
日差しが強いこの季節、コンクリートも我々のお肌も乾燥は禁物です。
舗装止めブロックの基礎をつくるため、重機で砕石を投入しています。
なぜ砕石?砂利ではダメなんですか?と思いますよね。
砕石は粉砕機で砕いているので角があり大きさも不揃いですが、転圧をすると砕石同士がしっかりと噛み合い地盤が締まります。
海や川の流れで角が取れ、丸みのある砂利では転圧しても噛み合わないのです。
砕石と砂利。似てるけれど役割が全然違います。
水は通すが土砂は通さない。地盤のヒーロー、吸出し防止材を敷設しています。
しかし、その能力を発揮するにはラップ長(重ね代)が大事です。
ラップ長がないと隙間から土や砂が流れ込んでしまいます。
決められたラップ長は10~20cm、きちんと重ねてしっかり確認。
これで土砂の吸出しが防止できて安心!(ラップ調で)
今日は覆土ブロックの検収です。
たくさんあって気が遠くなりそう...。
しかし!材料検収は非常に重要な工程です。気を抜く訳にはいきません。
搬入された覆土ブロックが注文どおりの数量、規格、品質でないと大問題ですから。
材料検収のおかげで、自分で購入した服などもタグを取る前にサイズや色をよーく確認するようになりました。
どこまでも続くなが~い基礎ブロック。
もちろん1本ものではございません。
コンクリートのブロックをひとつずつ重機で吊りあげてコツコツと連結したものです。
出来形確認も無事終えてようやく基礎ブロックが完成しました。
次は帯工ブロック。
連節ブロック張りはまだまだ続きます。
法面が侵食されるのを防止するため芝を張っています。
傾斜があるので、張った芝がずれないように目串を打ち込んで固定しています。
串をみると串焼きとか食べたくなってしまいます。
そんな気持ちを抑えて、芝が張れたら目土(めつち)を芝の上に散布します。
芝を目土で覆うことにより根の乾燥を防ぎ、苗が根付きやすくなります。
これからどんどん芝が育ち法面が緑で覆われることでしょう。
緑の山々と穏やかに流れる久慈川をバックに、はいっチーズ!
ではなくて、ドローンを用いて出来形測定をするために必要な標定点の測量をしています。
今日はあいにくの曇り空ですが、ドローン撮影は点群データを取るためなので全く問題ありません。
完成後のドローン撮影はもっと快晴だといいな。
またまたトラックスケールの出番です。
過載積は大きな事故の原因になりかねません。
ましてや、もうすぐ待ちに待ったゴールデンウィーク!
皆が楽しくGWを満喫できるよう、トラックの体重はトラックスケールでしっかり管理します。
我々の体重管理は自己責任。GW明けが恐ろしい...。
「撒出し」とは、運んできた土をブルドーザーで層状に敷き広げることです。
丁寧に土を均す「敷き均し」よりも少し荒々しい感じがしますが、
規定の高さになるまで何層も撒出しと転圧を繰り返し強い地盤を作ります。
ようやく13層目まで到達しました。ゴールまであと少し。
がんばれICTブルドーザー!
日中はポカポカ陽気の今日この頃。
そろそろ熱中症対策も考えなければいけませんね。
バックホウのバケットを専用の法面バケットにチェンジして、いざ法面整形へ!
バケットの底を器用に使って斜面を平にしています。
法面バケットと、ICTと、熟練のオペレーターさんの合わせ技で法面を効率的かつ綺麗に整形しています。
現場事務所にある桜が満開になりました。きれいでしょう?
景観を良くするために現場事務所にお花を植えることはありますが、
しばらくはその必要はなさそうです。
通行人の方々も時折足を止めて眺めています。
素敵な場所に現場事務所を建ててよかった!
我々の頼れるICT建機、バックホウとブルドーザの刃先精度確認をしています。
ICT建機を使用して施工する場合、各工種や建機に応じた精度確認を行うことになっているのです。
バックホウとブルドーザが計測した3次元座標の精度はばっちりでした!
現場から見える山が淡いピンク色に染まってきました。
もうすぐ現場周辺の桜が見ごろを迎えるようです。
盛土をする前に、バックホウで段切りをしています。
段切りとは、斜面に盛土する時に新しい土が地滑りなどを起こさないよう階段状に地盤を削ることです。
見てください!(写真2枚目)オペレーターさんの丁寧で繊細な重機さばきで綺麗な階段ができました。
この階段の上に盛土をするので見えなくなってしまうのが残念ですが、
盛土の下で地滑りを防ぐ大切な役割をしています。
すっかり暖かくなって桜の蕾が膨らみ始めた今日この頃。
めずらしい形の、しかも工事車両っぽくない色の車が颯爽と道路を走っています。
この車は、道路を綺麗にする道路清掃車です!
車の前方についてるブラシを回転させて道路に落ちているゴミや土砂を巻き上げて回収しています。
こんな天気の良い日は道路清掃車でドライブも悪くないですね。
山になっている土砂は現場で発生した残土です。
トラックが運んできた残土を、数台のバックホウがふるい落としています。
バックホウが装着しているのは先日ご紹介したスケルトンバケット!
スケルトンバケットは網目になっているので、土砂に含まれる大きな石と土にふるい分けることができます。
残土はきちんとふるい分けし、砕石や流用土として再利用します。
えっ?バックホウが川の中を掘削?
これは、河道掘削という工事をしているところです。
洪水時の河川水位を低下させるため、川底に堆積している土砂を取り除いて水が流れる面積を広くしています。
近年、豪雨により川の水位が上がり洪水災害となってしまうケースが増えています。
河道掘削で洪水から街の安全を守ります!
先日、土砂運搬開始に伴い、ダンプトラックの運転手に対して安全運行指導を行われました。
土砂運搬時における様々な厳守事項を確認しました。
厳守事項には過積載の禁止、ヘルメット着用、地元車・農耕車最優先、荷台を下げてから動くなど専門的なことから
制限速度の厳守や運転中の携帯電話使用禁止など、一般のドライバーとしての常識もありました。
それらの厳守事項を必ず守ることを約束し、安全運転で土砂を運搬しています!
今日はインターシップ実習生の皆さんが来てくれました!
インターシップとは、学生さんが在学中に企業などで就業体験をすることです。
実習生の皆さんは、寒さも忘れて施工中の現場を興味深く見学していました。
現場だけでなくパソコンで3D画像を動かしてみたり興味津々な様子。
短い時間でしたが、建設業のいろいろを体験していただきました。
我々も若い実習生のみなさんとお話ができて楽しかったです!
いつ見てもバックホウはかっこいいですよね...ん?バケットがいつもと違うような...。
それもそのはず、このバックホウは、スケルトンバケットという網目状になっているバケットをつけているのです。
網目より小さな土や砂利はバケットから落ちるため、ふるい作業や川底の採石作業などにとても便利です。
スケルトンといっても透明ではなく、土砂中の大きな石や砕石などをふるって取り除いています。(じゃあなぜスケルトン?)
このように、用途に応じてバケットを替えて作業しています。
工事現場では、立入禁止区域や道路の安全確保、敷地の仮囲の為にオレンジネットがあちこちに設置されています。
ネット素材なので軽量で設置も簡単。柔らかいので万が一人に当たってしまっても痛くありません。
もちろん、オレンジ色以外にも緑色とか黄色もありますが、工事現場で使うならやっぱりオレンジ色ですよね。
オレンジ色は暖かいイメージの反面、目立つので注意を引きやすい色です。
みなさんもオレンジネットを見かけたら危ないので近づかないようにしましょう。
今日は現場周辺のゴミ拾いを行いました。
普段は車で通るので気づきませんでしたが、よく見ると細かいゴミがたくさん落ちているのに驚きました。
工事中はなにかとご迷惑をお掛けしたりご協力いただいている近隣住民の皆様へ感謝の気持ちを込めて、
また、企業の社会的責任を果たすために清掃活動を定期的に行っています。
こうした活動が作業員みんなの清掃意識を高め、いつもクリーンな工事現場を維持しているのですね。
工事車両が通るための道路、工事用道路を作っています。
仮設とはいえ工事車両が安全で円滑に走行できるようしっかりと作ります。
見てください!路盤材をトラックに積込む写真(左)(上)に綺麗な虹が写っています!
日頃から安全第一を心がけ懸命に作業する私たちに神様からの贈り物でしょうか。
寒いけれどこのように晴れた日は作業がはかどります!
長いはずだった冬休みはあっという間に終わりました。
たっぷり休息を取りリフレッシュできたので、改めて安全第一で頑張っていこうと思います。
あれ?青空を泳いでいるのは鯉のぼり・・・?もう?と思ったら吹き流しでした。
吹き流しは鯉のぼりと違って風の強さを目視で確認できるかなり重要なアイテムです。
クレーン作業などは強風の時に行うとクレーンがバランスを崩して倒れ大事故につながってしまうので、吹き流しの状態で作業の可否を判断します。
右の写真のように吹き流しと風速のめやすも掲示しています。
高速道路にも吹き流しはあるので覚えておくと安心ですね!
真冬のコンクリートは養生がとても大事です。
コンクリートは外気温が暖かいと早く固まり、寒ければ固まるのが遅いです。
さらに気温が低いとコンクリートは凍結します。凍結すると組織が破壊され強度が低くなり、ひび割れや変形などの原因になってしまうのです。
そこで、ジェットヒーターで暖めてブルーシートで覆いコンクリートが凍結するのを防ぎます。
まるで巨大な布団乾燥機ですね。寒いので私もあの中に入ってぬくぬくしたいものです。
堤防の浸食や河床の洗堀を防止するために行う根固め工。
根固め工には割栗石を充填した2tの袋詰玉石をたくさん使います。
型枠に袋材を装着してバックホウで割栗石を投入し、重量を確認したら口絞りロープを結束して完成!
袋の中身はだいぶ違いますが、クリスマス前のサンタクロースになった気分です。
ちなみに袋の中に入れる割栗石というのは、岩石を人工的に割って作る石材のことです。
粒が大きく重いため、石同士が嚙み合って崩れにくいという特徴があります。
堤防の法面をコンクリートブロックで覆い水流によって堤防が浸食されるのを防ぐ工事をしています。
法面に敷き詰めているのはカーペットのような吸出し防止材。
しわにならないよう平滑に、吸出し防止機能を維持するために上流面のシートを上にして重ねます。
シートの重ね幅は決められた長さになるように重ねていきます。
寝転がりたい衝動を抑えながら丁寧に敷いています。
吸出し防止材は土砂の吸出しを防止したり川の流れや波などにより堤防の表面が削り取られるのを防いでくれます。
ブロックの下で大事な仕事をしている縁の下の力持ちなのです。
仕事に集中しすぎて久慈川の紅葉はいつのまにか見頃を過ぎてしまいました。
しかし、川辺にはまだすこし赤やオレンジに色づいている木々があって私たちの心を癒してくれます。
今日はプレキャスト小口止めブロックを敷設しました。
小口止めブロックとは、ブロック積み擁壁の両端が浸食されるのを防護するために、コンクリートで横方向に仕切ったブロックです。
プレキャストの小口止めブロックは現場打ちと比べて型枠の組立作業の省略と工期の短縮になります。
ブロック同士を連結金具でしっかり固定することができるので施工時も安全ですね。
私たちは河川の洪水や氾濫を防ぐため水際で護岸工事をしています。
油漏れなどの水質汚染を防止するための対策は、以前この記事でワニさんの緊急油処理ボックスをご紹介させていただきました。
水際での作業は、突然の気象変動や増水など予測できない危険が伴いますので、安全対策が最も重要になります。
安全対策としては、作業員の安全を確保するために救命浮き輪が設置されています。
護岸工事は技術だけでなく、環境への配慮や安全対策が不可欠なんです。
今日はドローンで起工測量を行いました。
天気がよく風も穏やかでまさにドローン日和。
ドローン測量では、測量の精度を高めるために正確な座標が分かるポイントを地上に設置する必要があります。
トータルステーションで正確に測量して対空標識(写真中央)を設置します。
対空標識はドローンで上空から撮影したときに写真上で確認できる目印となります。
だからこのような模様になっているんです。
準備が整ったらLet's fly a drone!
安全掲示板には安全スローガンや無災害記録表、玉掛ワイヤーロープの点検色など大事なことが掲示されています。
工事に携わってない方が見てもなんのことやら…と思われるものもありますね。
それもそのはず、安全掲示板とは、現場で働く作業員に知らせるための掲示板です。
現場休憩所の目立ちやすいところに設置し、作業員が安全掲示板を見て安全を常にこころがけられるようにしています。
掲示板の中で私のお気に入りは弊社の安全スローガンです。
「安全管理で災害ゼロと時間管理で効率化 両立できるよ二刀流」
今日も安全施工の徹底と効率良い施工の二刀流を心がけて頑張ります!
黄色い三角旗や色とりどりの、のぼり旗が風になびいています。秋祭りでも行われているのでしょうか・・・。
残念ながら秋祭りではありませんでした。工事現場では安全を第一に考え、このようにして三角旗やのぼり旗を掲げて注意喚起をしています。
写真左写真1枚目の黄色い三角旗は、バックホウのアームが架空線に接触しないように、架空線よりもけっこう下に掲げられています。
また、ダンプトラックや重機回送車など、高さのある工事車両が接触しないよう注意喚起をしています。
もしも架空線に接触・切断してしまったら、影響は計り知れません。「↑架空線注意」ののぼり旗でさらに注意。
現場内を走行する車両にも、たくさんの色鮮やかな「徐行」「路肩注意」「関係者以外立入禁止」ののぼり旗で注意喚起をしています。
安全第一がモットーです!
快適トイレが設置されました!
皆さんがイメージする工事現場のトイレって、「汚い、暗い、男女兼用」など、少しネガティブなイメージではないですか?
実は私もこの会社に入るまではそんな風に思ってましたが全然違ってました。
それもそのはず。国土交通省は、工事現場で女性が活躍しやすいよう2016年に快適トイレの設置を標準化しました。
トイレが男女分かれていて、中は清潔で明るくとても使いやすいです。
トイレが快適だと男女ともに気持ちよく働くことができますね。
たかがトイレ、されどトイレです。
今日は穏やかに流れる久慈川の川辺を除草しています。
久慈川は茨城県、福島県、栃木県との県境に位置する八溝山から太平洋にかけて流れている一級河川です。
多くの魚類や水生植物が生息しており、日本で有数の鮎の釣り場としても有名ですね。
茨城県の豊かな自然環境を象徴する川です。
除草もICTで...というわけにもいかず、自走式草刈機や刈り払い機で除草します。
ヤギの群れがやってきてこの草を食べてくれないかな...などと考えてたらあっという間に綺麗になっていました(写真右写真3枚目)。
除草にはICTもヤギも必要ありませんでした!
今日は現場に大勢の人がいますね。
なにやら緊張感ただよう雰囲気・・・いったいなにが行われているのでしょうか。
実は、今日は国交省合同安全パトロールが行われているのです。
現場の担当者が国交省の方々と一緒に現場を巡回して現場の状況や設備、機器などさまざまな観点から災害につながる危険がないかをチェックし、
少しでも問題のある箇所が確認されるとすみやかに是正するよう指示してくださいます。
安全パトロールはちょっと緊張しますが、私たち作業員の安全を確保するばかりでなく、安全に対する意識をより高めてくれます。
当現場は水際の作業なので水質汚染防止に努めています。
油流出を防ぐため、使用機械等は始業前点検を行っています。
それでも万が一油流出事故が発生した場合に備えて、緊急油処理ボックスを常備しています。
ボックスの中には、油漏れにすぐ対応できるさまざまな対策品が入っています。
オイルゲーター(写真左下下の写真1枚目)とセルソーブ(写真中央下下の写真2枚目)は100%天然素材の油吸着材です。
植物や動物や水生生物に害を与えることなく使用でき、吸着した油を再浸出することはありません。
さらにオイルゲーターは吸着した油を水と二酸化炭素に分解することができます。すごい!
そのほかにもオイルフェンスやオイルマット、消火器、防塵マスク、防塵メガネ、ゴム手袋などが入っています。
環境被害を最小限にするためにもこれだけ備えておけば安心、とワニ君も言ってます。
ようやく秋らしくなり食べ物の美味しい季節になりました。
現場周辺ではおいしくて安くてボリュームのある食事が頂けるのでついつい食べ過ぎてしまいます。
詳しくは現場周辺情報をご覧ください。
ICTブルドーザーで掘削をしています。
前方についているブレードでパワフルに土砂を押し出しています。
ブレードの上についてるかたつむりの触角のようなものがGPS受信機です。
GPSでブルドーザーの正確な位置情報を取得し、3次元データに沿ってブレードを自動制御しています。
丁張の工程がいらないので驚くほど順調に作業が進んでおります。
厳しい残暑もようやく落ち着き今日は心地よい秋晴れとなりました。
いよいよICT施工のスタートです。
ICT施工には多くのメリットがあります。
起工測量ではドローン撮影で3次元データを作成したため、従来の測量よりも作業時間が短縮されました。
ICT建機は3次元データを活用して正確な位置情報を取得しオペレータに提供するので、作業員は熟練度に左右されず高精度な施工が可能となります。
また、通常の工事では、測量や作業補助など、作業員が建機の周辺で業務を行っているので、建機の稼働中は常に危険を伴なっておりました。
ICT施工では正確なデータが取得できるため、測量する作業員が不要になるのでそういった危険がなくなります。
そういえば現場に作業員が見当たりませんね...。
以上のように、ICT施工は施工の効率と精度が向上し、なによりも安全性が向上するのは大きなメリットです。
工事車両を誘導する時、大きな声を出したりホイッスルを鳴らしたり、活気がありますね。
しかし!この音は近隣の皆さまにとっては騒音でしかありません。
そんな問題を解決するために導入されたのがこの「工事車両音声誘導システム FM-Navi SOK-F100」(1枚目の写真)です。
微弱なFM周波数を利用して重機のオペレーターの音声を工事車両内のラジオで流すことができます。
つまり、オペレーターがラジオの周波数を合わせるだけで誘導する合図や指示がラジオから聞こえてくるのです!
オペレーターの声による具体的で確実な誘導が可能となりました。
また、交通誘導員を配置する必要がないので誘導員を削減できるだけでなく、誘導員と重機との接触事故など危険がなくなります。
2枚目と3枚目の写真は、このシステムを活用してダンプトラックをバック誘導しているところです。
大きな声やホイッスル音は無くとも円滑に作業は進んでおりました。
騒音対策だけでなく確実な誘導、人員の削減、接触事故の軽減などさまざまなメリットがあり、安心かつ安全に作業することができますね。
設計書通りに、且つ安全に施工を行う為には正確な位置情報を取得している必要があります。
ICT建機が取得する3次元座標データを施工履歴データといい、出来高・出来形管理に活用します。
そのため、ICT建機を使用して施工を行う場合、各工種や建機に応じた精度確認試験を行います。
施工履歴データと、トータルステーション等の測量機器により計測された座標の差分が要求精度内かを確認します。
今日は掘削工におけるバックホウとブルドーザーの精度確認試験を実施いたしました。
作業員のみなさん、暑い中てきぱきと作業していました。
試験結果は見事合格!ICT建機の位置情報は要求精度内でした。
これで安心してICT施工がスタートできます。
大型のダンプトラックに土砂を積込み発生土受入場所に運搬します。
たくさん積んで運搬すれば効率がいいですよね。
しかし!最大積載量を超えて荷物を載せて走行してしまう(過積載)と土砂が落下たり、ブレーキやスピードの制御が難しくなるなど、
大きな事故の原因になってしまいます。
そもそも過積載は罰則の対象になっていますので、土砂を積み込む際は十分な注意が必要です。
私たちは過積載防止対策としてトラックスケールを導入しています。
トラックスケールとは、トラックに積載された積荷の重量を計測する大型計量器です。
このトラックスケールは小型で軽量なので持ち運びができ、場所を選ばず使用することができます。
空車のトラックをスケールの上に配置してバックホウで土砂を積込み計測します。
最大積載量を1Kgでも超えると過積載と判断されます。正しく測って余裕をもった積載量で運搬しています!
夏期休暇中、日本では酷暑・地震・台風などいろいろありましたが、私はゆっくり体を休めてリフレッシュすることが出来ました。
現場も特に変わった様子はありませんでした。
しっかり充電できたので、また気を引き締めて作業していきたいと思います。
今日は土木安定シートを敷設しました。
土木安定シートとは、軟弱地盤安定のために使用されるシートです。
大きな土木安定シートを、現地盤の上に敷いていきます。
大きいシートとはいえ、広い現場なので何枚も必要ですね。
決められた重ね幅(ラップ長)になるよう重ねて敷いていきます。
シートを敷き終えたらその上から盛土をするのでシートが隠れてしまいますね。
土木安定シートは見えないところで軟弱地盤の安定に大きく貢献しています。
連日の猛暑、いや、酷暑で熱中症にならないよう弊社ではさまざまな対策をしています。
今日はその一部をご紹介しますね。
左1枚目の写真は熱中症対策応急キット。収納バックの中に熱中飴や冷却剤・イオン水などが入っていて、もしもの時に応急措置ができるようになっています。
右2枚目の写真は真夏の強い味方、空調服です。思ったより軽量で着心地が良く、なにより涼しくて作業がはかどります。
現場休憩所に設置されているのは暑さ指数(WBGT)測定器と注意喚起の看板です。
暑さ指数とは、気温と湿度と輻射熱の3つを取り入れた指数です。気温ではありませんよ。
測定器でWBGT値をリアルタイムで確認でき、看板を見ればその警戒レベルが簡単に判別できますね。
こまめにチェックして熱中症を予防しましょう!
工事の支障となる竹を重機で伐採しています。
といっても伐採専用の重機ではなく、油圧ショベルのバケット部分を伐採用のものに変えることで伐採の作業に活用できます。
次々と竹をなぎ倒していく重機は迫力満点ですね。
竹を伐採した後は根っこが残ります。
根っこは地中へ深く伸びているのですが、そんな根っこもショベルカーであっという間に取り除きます。
たのもしいですね。
伐採・除根はまだまだ続きます。
これより着手する久慈川に堤防を築く工事の様子を日々お伝えすることとなりました。
よろしくお願いします。
現場は久慈川が穏やかに流れる自然豊かな場所です。
左下の写真の看板を見ると、この近辺では友釣り(鮎釣り)ができるんですね。
鮎がいるということは綺麗な川である証拠です。
さっそく工事看板を設置しました。
工事の概要、期日、時間帯を近隣の皆さまに詳しくお知らせしています。
「作業は平日のみ」としっかりアピール。
工事現場の労働環境はとても良くなっています。
先日、令和6年度店社安全衛生大会が行われました。
今年で40回目となります。
工事現場で働く労働者を災害から守るため、安全衛生にかかる知識を深める目的で開催されるとても重要な大会です。
この大会に出席し、改めて安全に対する意識が高まりました。
いよいよ始まる築堤工事。竣工まで安全第一で頑張るぞ!